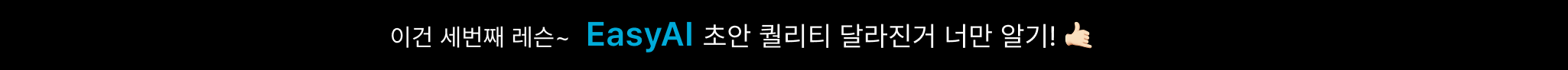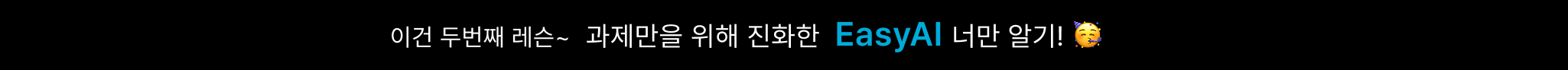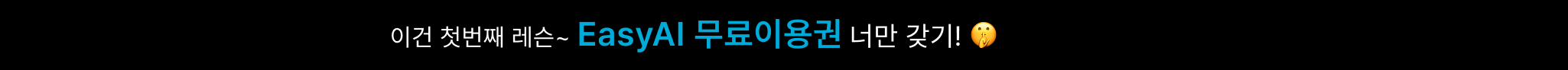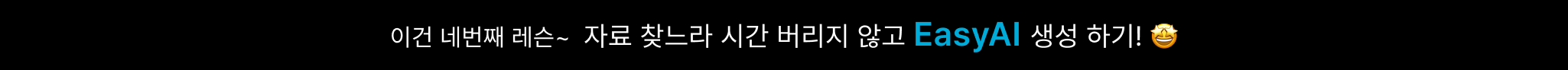방송대- 일본어문법 - 교재의 일본문화에 대한 이야기를 정리한 것 - 13강 속담
본 내용은
"
방송대- 일본어문법 - 교재의 일본문화에 대한 이야기를 정리한 것 - 13강 속담
"
의 원문 자료에서 일부 인용된 것입니다.
2024.04.03
문서 내 토픽
-
1. ごまをする아첨하다. 글자 그대로는 깨를 볶다라는 뜻이다. 볶은 참깨를 절구에 넣어 짓이기면, 참깨가 묻어 끈적끈적한 상태가 된다. 아부하는 사람이 다른 사람에게 끈적끈적 달라붙는 것과 비슷한 것에서 나온 표현이다. 또한 장사꾼이 거래를 할 때 손을 비비는 행동이 참깨를 으깨는 동작과 비슷하기 때문에 깨를 볶다라고 하면 아첨하다는 뜻으로 해석한다.
-
2. 月と鼈천양지차달과, 자라 라는 뜻이다. 한국어로는 하늘과 땅으로 표현하지만 일본에서는 달과 등껍질이 둥근 자라를 비유하여 만든 표현이다. 옛날부터 자라는 등딱지를 빗대어 동글이라고 했다. 보름달도 둥글지만 자라의 동그라미와는 전혀 달라 비교가 안되는 것을 말한다. 좋은 쪽을 달, 좋지 않은 쪽을 자라에 비유하기도 한다.
-
3. 漁夫の利어부지리 글자 그대로 어부의 이득 이라는 뜻이다. 어부지리라는 것은 두 사람의 싸움에 제 3자가 예상치 못한 이득을 얻게 되는 것을 말한다. 전국 시대의 중국의 고사에서 유래한 표현이다. 강에서 조개와 도요새가 싸우고 있었다. 도요새는 조갯살을 먹으려고 부리를 조개 입으로 집어 넣었고, 조개는 도요새의 부리를 물었다. 이를 본 어부가 둘 다 잡아갔다는 내용이다.
-
4. 頭?して尻?さず머리는 감추고 엉덩이는 감추지 않는다. 꿩은 풀 숲에서 머리를 긁고 있어도 꼬리가 다 드러나 있는데서 유래한 말이다. 나쁜 일이나 결점을 가리려고 해도 일부는 어디선가 드러나고 만다는 의미이다.
-
5. 後は野となれ山となれ나중 일은 내 알게 뭐냐. 직역하면 "나중에는 들이 되라, 산이 되라." 라는 뜻이다. 이것의 의미는 나중 일은 어떻게 되든 상관 없다라는 의미이다.
-
6. ?蜂取らず이것저것 탐내다가 하나도 얻지 못함거미가 자신이 둥지에 걸린 あぶ(등에)와 蜂(벌)을 둘 다 취하려다 결국 둘 다 잃어 버렸다는데서 유래한 말이다. 둘 다 동시에 손에 넣으려다가 양쪽 모두 손에 넣을 수 없다는 뜻으로 쓰인다.
-
7. 案ずるより産むのが易い걱정하는 것보다 실행하는 것이 쉽다. 아이를 낳기 전에는, 이것저것 걱정을 하는 법이지만, 실제로 낳아보면 그 정도로 큰일은 아니라는 것에서 유래한 표현이다. 무언가를 하기 전에 이것저것 걱정을 하게 되지만, 실제로 해보면 의외로 간단하게 할 수 있는 법이다.
-
8. 石の上にも三年돌도 십년을 보고 있으면 구멍이 뚫린다직역해 보면 '돌의 위에도 3년' 이다. 차가운 돌이라도 참고, 3년이나 앉아 있으면 따뜻해 지는 법이라는 말에서 유래한 표현이다. 아무리 괴로운 일이라도, 참고 노력을 계속해 나간다면 반드시 보답받는다는 교훈을 준다.
-
9. 石橋をたたいて渡る돌다리고 두드리고 건넌다 . 한국에서도 글자 그대로 사용하고 있는 표현이다. 돌로 만들어졌지만 튼튼한지 다리라도 일부러 두드려서 안전을 확인한 다음 건넌다는 것에서 유래한 말이다. 아주 주의깊게 행동하는 것을 가르킨다.
-
10. ?者の不養生남의 건강을 돌볼 의사가 오히려 섭생에 유의하지 않음 ((언행이 일치하지 않음의 비유)). - 의사의 불양생 이라고 읽습니다. 의사는 사람의 건강에 대해서는 이것저것 조심하고 있지만, 자신의 건강에는 별로 신경 쓰지 않는 것에서 유래한 말이다.
-
1. ごまをするごまをするという慣用句は、物事を丁寧に行うことを意味しています。これは、ごまの種を手で丁寧に擦り潰す動作に由来しています。この言葉は、仕事や日常生活において、細かな部分にも注意を払い、丁寧に行うことの大切さを表しています。ごまをするように、物事に真摯に取り組み、丁寧に行うことは、良い結果を得るために重要です。この言葉は、仕事や生活の中で心がけるべき姿勢を示唆しているといえるでしょう。
-
2. 月と鼈「月と鼈」という言葉は、本来は月と亀の比較を表す言葉ですが、ここでは月と鼈(かめ)を比較することで、全く異なる性質のものを比較することの難しさを表しています。月は美しく遠く離れた存在であるのに対し、鼈は地上を這う地味な存在です。このように、全く異なる性質のものを比較することは適切ではありません。この言葉は、物事を適切に評価し、比較することの大切さを示唆しています。同じ物差しで全ての物事を評価するのではなく、それぞれの特性を理解し、適切に評価することが重要だと言えるでしょう。
-
3. 漁夫の利「漁夫の利」とは、偶然に得られた利益のことを指す言葉です。漁師が網を引き上げると、時には予期せぬ大物が獲れることがあります。このような偶然の幸運を「漁夫の利」と呼びます。この言葉は、計画的な努力だけでなく、偶然の要素も成功の要因となることを示しています。人生においても、計画的な努力と同時に、予期せぬ幸運に恵まれることも重要です。しかし、「漁夫の利」に頼りすぎるのは危険で、計画的な努力と偶然の要素のバランスを保つことが肝心だと言えるでしょう。
-
4. 頭?して尻?さず「頭?して尻?さず」という言葉は、物事を適切に行えないことを表す言葉です。頭を下げて謝罪するが、最後まで謝罪しないことを指しています。つまり、物事を最後まで適切に行えないことを表しています。この言葉は、物事を最後まで責任を持って行うことの大切さを示唆しています。物事を始めたら、最後まで責任を持って行い、適切に完遂することが重要です。半ば途中で投げ出したり、最後まで責任を持たないことは適切ではありません。この言葉は、物事に対する責任感の大切さを教えてくれるのだと言えるでしょう。
-
5. 後は野となれ山となれ「後は野となれ山となれ」という言葉は、自分の行動の結果に責任を持たず、後のことを気にしないで済ませようとする態度を表しています。自分の行動の結果に責任を持たず、後のことを気にせずに行動することは、適切ではありません。この言葉は、自分の行動に責任を持ち、その結果に対して真摯に向き合うことの大切さを示唆しています。自分の行動の結果に責任を持ち、それに対して真摯に向き合うことで、より良い行動につながるはずです。この言葉は、自己責任の重要性を教えてくれるのだと言えるでしょう。
-
6. ?蜂取らず「?蜂取らず」という言葉は、危険なことに手を出さずに、安全に行動することの大切さを表しています。蜂の巣に手を出せば、蜂に刺されるリスクがありますが、それを避けることで安全に行動できます。この言葉は、危険なことに手を出さずに、慎重に行動することの重要性を示唆しています。時には、危険を冒してでも何かを成し遂げようとする気持ちもわかりますが、安全を第一に考え、慎重に行動することが大切です。この言葉は、危険を避けつつ、確実に目的を達成する方法を教えてくれるのだと言えるでしょう。
-
7. 案ずるより産むのが易い「案ずるより産むのが易い」という言葉は、あまり心配せずに行動することの大切さを表しています。物事を過度に心配したり、慎重に考えすぎると、かえって行動が遅れてしまうことがあります。この言葉は、心配するよりも、まずは行動に移すことが重要であることを示唆しています。もちろん、完全に無計画に行動するのは危険ですが、適度な準備と勇気を持って行動することが大切です。この言葉は、行動力と前向きな姿勢の重要性を教えてくれるのだと言えるでしょう。
-
8. 石の上にも三年「石の上にも三年」という言葉は、時間と努力が必要であることを表しています。石の上に座り続けても、すぐには座り心地が良くなるわけではありません。同様に、何かを成し遂げるためには、長期的な努力と忍耐が必要です。この言葉は、物事を成し遂げるには時間がかかることを示唆しています。一朝一夕には結果は出せず、粘り強く努力を続けることが重要です。焦らずに着実に前進することが、目標を達成するための鍵となるのだと言えるでしょう。
-
9. 石橋をたたいて渡る「石橋をたたいて渡る」という言葉は、物事を慎重に確認しながら進むことの大切さを表しています。石橋を渡る際には、その強度を確認するために石をたたいて確認するのが賢明です。同様に、物事を進める際にも、慎重に確認しながら進むことが重要です。安易に進むのではなく、リスクを確認し、慎重に行動することで、より確実に目的地に到達できるのです。この言葉は、安全と確実性を重視した行動の大切さを示唆しているといえるでしょう。
-
10. ?者の不養生「?者の不養生」という言葉は、自分の健康管理を怠ることの危険性を表しています。医者や医療従事者は、自身の健康管理を疎かにしがちですが、それは適切ではありません。自分の健康が第一であり、それを守らなければ、他者の健康も守れません。この言葉は、自分自身の健康管理の大切さを示唆しています。自分の健康を第一に考え、適切に管理することで、より良い仕事や生活を送ることができるのです。自分の健康を大切にすることは、自己責任であり、同時に他者への責任でもあるのだと言えるでしょう。